

講演会|〈ニ峠六宿〉ユニークべニュー事業
勝海舟とはどんな人生を送ったのか。剣術修行を終え、西洋の学問を勉強していた貧乏書生時代、佐久間象山先生との交流はご存知の方も多いかと思います。
静岡時代に交流のあった人々との関係性を紐解くとともに、静岡に残る海舟宛書簡や書類の内容をご紹介します。

著述業・勝海舟玄孫
慶應義塾大学文学部仏文科卒業
田中貴金属工業株式会社秘書室・広報室勤務を経て「るるぶ」「東京人」など旅行、紀行雑誌、企業広報誌などを主な対象に執筆活動をしつつ、勝海舟の子孫としての講演や各種プロジェクトに参加。
「勝海舟関係写真集」(出版舎 風狂童子)
咸臨丸子孫の会副会長、勝海舟顕彰会顧問、勝海舟の会名誉会長、東京龍馬会顧問、高知県観光特使、長崎市観光大使、三重県松阪市ブランド大使、東京都港区観光大使
勝海舟とはどんな人生を送ったのか。剣術修行を終え、西洋の学問を勉強していた貧乏書生時代、佐久間象山先生との交流はご存知の方も多いかと思います。行き来するうちに海舟の妹、順が象山先生に嫁ぐことになり、その後も象山塾は有能な人材を輩出していきました。生涯の付き合いになる豪商達、また意外な大物武士など、海舟はどんな人たちからどのような影響を受けたのか、それを次世代にどう恩送りしていったのか、お伝えします。また、静岡時代に交流のあった人々との関係性を紐解くとともに、静岡に残る海舟宛書簡や書類の内容をご紹介します。

講演会|〈ニ峠六宿〉ユニークべニュー事業
東海道の難所であった宇津ノ谷峠に、日本初の有料トンネルとして開通。明治9(1876)年に開通したため、「明治のトンネル」と呼ばれています。
現役のトンネルとしては初めて国の登録有形文化財にも登録されました。
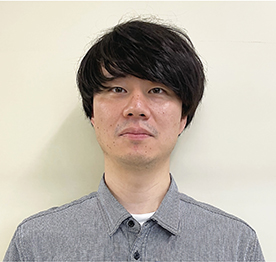
平成30年度に静岡市役所に事務(学芸員)として採用。市内の文化財の保存・活用業務に従事している。令和6年12月に文化庁の認定を受けた『静岡市文化財保存活用地域計画』を担当した。現在、地域総がかりで文化財の保存・活用をしていくための仕組作りに向けて日々の業務をしている。
明治のトンネルは正式名称を明治宇津ノ谷隧道と言います。明治9年に開通したトンネルが、火災で崩落したものを、その一部を利用する形で修築したものが現存しています。旧東海道に沿ったルートで、総延長203メートルに及びます。坑口から坑内にわたって全面的に煉瓦造であることが特徴であり、明治隧道の名称で親しまれています。この地にトンネルが開通した経緯等を東海道宇津ノ谷峠の歴史を踏まえつつ分かりやすく説明します。
講演会後、講師とともに明治のトンネルの散策にご案内します。

講演会|〈ニ峠六宿〉ユニークべニュー事業
時代の荒波にのまれながらも、ダイナミックな歴史を彩った姿を、
彼の生家である国の登録有形文化財の次郎長生家(旧高木邸)で当時を解説します。

60歳 郷土史研究家。次郎長生家のある地元に暮らし、次郎長翁を知る会理事・運営委員として次郎長に関する研究と功績を語り継ぐ活動を行っている。
次郎長は1868年に官軍の管理下で、駿府周辺の街道と清水港警護を任されます。過去の罪を赦された後は、社会事業家として活躍。駿府に移住する旧幕臣の世話や浪士の取締りに従事し、清水港の近代化推進や横浜との航路を整備していきます。富士裾野での開墾を試み、遠州相良油田(現在の牧之原市)の開発に協力し、また青年を集めた英語塾を開いたりと開明的な一面もありました。さらには医療や女性の教育分野でも貢献し、晩年は船宿「末廣」を営みます。74歳で死去するまでの次郎長の半生は、表社会で数々の事業に携わり、彼の功績は多くの方々に讃えられています。そんな社会事業家半生をダイナミックに講演していきます。お楽しみに。

講演会|〈ニ峠六宿〉ユニークべニュー事業
江戸城無血開城に向け、徳川慶喜より命を受け
西郷隆盛との直談判に向かった

昭和17年(1942年)、静岡県静岡市(旧清水市)生まれ。
母親が望嶽亭を代々守ってきた家の出身と云うこともあって、静岡・山岡鉄舟会が2004年、静岡に発足して以来、会の活動に携わっている。
明治元年、西郷隆盛と会談する為に静岡に向かう山岡鉄舟は、薩埵峠で官軍に追われて望嶽亭に飛び込みました。そこは由比宿と興津宿の『間の宿(あいのしゅく)』で、江戸時代には脇本陣も務めた望嶽亭の蔵屋敷で、鉄舟は漁師姿に着替えて隠し階段を降り、海から小舟で脱出。その後、清水江尻の侠客・清水次郎長の元で身を隠し、駿府で西郷隆盛と会談し、『無血開城』が成功…。命を受け、決死の覚悟で挑んだ鉄舟の生き様と、望嶽亭が歴史の波にのまれていく一幕を語ります。会場では特別に、鉄舟が置いていったフランス式拳銃も見学いただきます。

講演会|〈ニ峠六宿〉ユニークべニュー事業
時に修行の場として、時に戦国の砦として、
最後に平和を見渡す頂きとして久能山は存在した。

浜松市生まれ。皇學館大学文学部神道学科を卒業。
平野神社(京都市)に奉職、一時飲食業の経験を経て、生國魂神社(大阪市)に奉職。その後、平成27年より久能山東照宮に奉職。
久能山は飛鳥時代に「久能寺」が開かれ、鎌倉時代には聖一国師など高名な僧侶も訪れた地です。時に信玄が信濃から侵攻し、南海の砦「久能城」として久能山を支配。家康がそれに対抗しました。いにしえより僧侶の修行場として機能し、戦国時代には軍事戦略上の砦として重要な役割を果たした時代もありました。平安が望まれた家康統治の時代には、駿河湾と伊豆半島、西は御前崎迄が見渡せる事から、安全保障上の海上監視の役割も果たしました。今では煌びやかな国宝として久能山東照宮がありますが、講演会では江戸幕府が開かれる以前の、久能山における知られざる役割と機能を、歴史エピソードも添えて語られます。

講演会|〈ニ峠六宿〉〜ユニークべニューを活用したオンラインシンポジウム
東海道17番目の宿場町、興津宿。大正から昭和にかけて、
政財界人の多くの重鎮がこの地を訪れた。西園寺公望の助言を求めて―。

郷土史家。静岡県沼津市生まれ。
旧清水市職員として文化財保護を担当。著書は『古代中世久能寺とその芸能』(2019)ほか。
近代日本において、最後の元老として内閣総理大臣を選定できる役割を担い、昭和天皇に意見を言える立場にもあった西園寺公望。そんな国家の重臣が別荘として築いた屋敷が興津坐漁荘です。激動する日本政治の数々の局面であってもブレることなくリベラルな姿勢を貫き、興津から当時の政治を動かしました。西園寺の知られるざる素顔や地域に根差す歴史エピソードや坐漁荘の魅力が語られます。